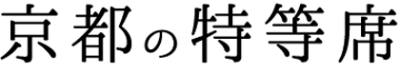「食材が怖がらない」 包丁とメンテナンスの専門店「食道具竹上」
一年の終わりが近づき、台所道具の手入れや新調を考えている人も多いのではないでしょうか。今回訪ねたのは、「庖丁(ほうちょう)コーディネーター」として活躍するオーナーが営む「食道具竹上」。職人の手によるオリジナルの包丁とラボ(刃付け、調整、修理などを行う工房)、キッチンを併設した空間には、「作る」と「食べる」をつなぐ真摯(しんし)な思いがありました。
■暮らすように、小さな旅にでかけるように、自然体の京都を楽しむ。朝日新聞デジタルマガジン&Travelの連載「京都ゆるり休日さんぽ」はそんな気持ちで、毎週金曜日に京都の素敵なスポットをご案内しています。 (文:大橋知沙/写真:津久井珠美)
買った時よりも切れるように、よみがえらせる

和食の料理人は、日々包丁の手入れを怠りません。柳刃、出刃、薄刃など、食材や切り方によって多様な包丁を使い分けるのも日本独特の調理の文化。「切れ味」が料理の味を左右すると、日本人は学んできたのでしょう。

そんな日本の包丁文化を今に伝え続けているのが、「食道具竹上」のオーナー・廣瀬康二さん。京都の老舗包丁店に16年間勤め、府内の南丹市で「庖丁コーディネーター」として独立して10年。丁寧で親身なメンテナンスに定評があり、プロの料理人から、どうしようもなく傷めてしまったと困る一般の人まで、廣瀬さんを指名して包丁を託します。

「うちの修理は“更生”です。買った時よりも切れるようにする。包丁自体のゆがみや反りを調整してから研ぎ、最後に天然の砥石(といし)で仕上げます。人工の砥石は安定して研げますが、最終調整は京都・丹波で採れる天然の砥石でないといけません。自然の砥石で研ぐと、刃の状態も自然のものに近くなる。食材への当たりが優しいんです」

そう話す廣瀬さん。よく切れ、食材を潰さない包丁は、切り口から風味やうまみが流れ出ないと言います。切れ味の良い刃物なら、誤って皮膚を切ってしまっても痛みを感じにくいと言われるのと同じこと。包丁の更生は「食材が怖がらない包丁にすること」と語ります。
「食べるということは、命をいただくということですから。栄養を逃さず、きれいに切られた食材はピンと角が立ち、むっくりと風味が際立ちます」
「作る」「食べる」「手入れする」をひと続きに伝えたい

先祖が薬屋として使っていた屋号「竹上」を受け継ぎ、庖丁コーディネーターとして10年ほどフリーランスで活動したのち、キッチンと工房を備えた店をオープンしたのは昨年のこと。熟練の鍛冶(かじ)職人が手仕事で仕上げるオリジナルの包丁をはじめ、使い勝手の良いまな板や砥石などがそろいます。ガラス張りのラボでは、購入した包丁をその人に合わせて調整する工程やメンテナンスの様子をつぶさに見ることができます。

「昔は、技術を盗(と)られるからと見えないところで作業していたものですが、今はモノではなくコトを売る時代です。どんなふうに包丁を更生しているのか見える方が、道具と向き合うということを知っていただける」
と廣瀬さんは話します。店の奥にキッチンを設けたのも同じ理由から。包丁の研ぎ方講習をはじめ、料理教室や多彩な食のイベントなど、包丁という道具の先にある人々の「暮らし」に、廣瀬さんの目は向けられています。

「偶然の出会いを意味する“セレンディピティー”という言葉がありますけど、それが生まれる場所になれたら。人と人とが学び、つながることで、今の時代に刃物が“生きる”と思うんです」

安価な包丁が簡単に手に入る今、手入れしながら長く使う包丁は手間のかかる道具でしょうか。キリリと研がれ、使い勝手の良い包丁が日々の料理を格段においしくするならば、それは道具以上の豊かさをもたらしてくれるはずです。一年を振り返り新しい年を待つこの時期、一生モノの包丁を迎えたり、いつもの包丁に新しい命を吹き込んだりする機会にしてはいかがでしょう。


朝日新聞デジタルマガジン&Travelより転載
(掲載日:2020年12月18日)