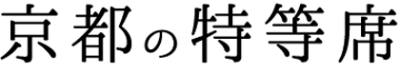京都に春の訪れを告げる「五大力尊仁王会」
伏見区にある世界遺産・醍醐寺は、1100年以上の歴史を紡ぐ真言宗醍醐派の総本山。広大な境内は醍醐寺の発祥である上醍醐、後に山裾に堂宇が建立された下醍醐で形成。下醍醐の五重塔は朱雀天皇が醍醐天皇の冥福を祈るために起工し、村上天皇の時代、951年に完成した国宝だ。また本堂にあたる国宝の金堂も、豊臣秀吉が紀州から移築させたもので、平安末期の様式が残る。

京都に春の訪れを告げるのが、醍醐寺で毎年2月23日に営まれる「五大力(ごだいりき)さん」こと「五大力尊仁王会(にんのうえ)」だ。全国から十数万人の参拝者が集まる寺最大の年中行事。五大力尊とは、不動明王や金剛夜叉明王など五大明王の総称で、その力を授かり、化身である五大力菩薩によって国の平和や国民の幸福を願うというもの。

法要が始まると、国宝の金堂で「五大力尊御影(みえい)」の授与が行われる。御影は京都の各家庭の玄関や、勝手口、駐車場などいたるところに貼られているお札で、京都では昔から馴染み深い。
五大力尊の分身であるお札が、影のようになって家や人を守り、あらゆる災難を払い除けるといわれる。境内には早朝から夕方まで、お札を求める人の長蛇の列が続く。
また金堂横に設けられた柴燈(さいとう)護摩道場では、護摩を焚きながら法要が行われる。大勢の山伏が集まり、法螺(ほら)貝を一斉に吹き鳴らす様は圧巻だ。法要の最後には加持祈祷が行われ、ご利益をさらに高めたい人がお札を預けたり、財布やカバンなどを清めたりする。
「五大力尊仁王会」の名物となっているのが、金堂前の特設舞台で行われる「奉納餅上げ大会」だ。五大力さんに力自慢がその力を奉納して無病息災、身体堅固を祈る奉納行事で、男性は150キロ、女性は90キロの紅白の大鏡餅を抱え上げ、そのタイムを競い合う。小学生、男性、女性の各部があり、優勝者は「横綱」として優勝タイムとともに境内入口の看板に名前が記される。
醍醐寺の法要に参加して、京都らしい春を堪能してみてはいかがだろうか。
製作著作:KBS京都 / BS11
【放送時間】
京都浪漫 悠久の物語
「世界遺産 醍醐寺~千年の歴史を見つめる~」
2025年2月10日(月・祝) よる8時~8時53分
BS11(イレブン)にて放送