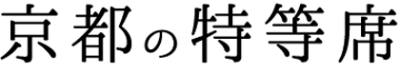写真家も魅了する可憐な桜の数々
京都には桜の名所が数多くあるが、プロの写真家も足しげく通う、“フォトジェニック”なスポットを紹介しよう。
叡山電車鞍馬線の鞍馬駅を降りると、そこは鞍馬山の麓だ。鞍馬街道を少し歩くと鞍馬寺の仁王門が現れ、そこから九十九折(つづらおり)参道を上るか、多宝塔駅までケーブルカーを利用することになる。鞍馬寺は奈良時代末期、鑑禎(がんちょう)上人が毘沙門天を安置したことに始まる。平安時代の女性文学者も多く訪れ、清少納言は「枕草子」で「近うて遠きもの くらまのつづらをりといふ道」と著している。境内には数多くの桜が咲き誇るが、鞍馬山の桜は雲珠桜(うずざくら)」と呼ばれる。これは品種ではなく、常緑の木々の間に点々と咲く様子が、馬具の吊り金具の「雲珠」に似ていることから命名されたもの。雄大な自然と歴史ある伽藍の中に彩りを添える桜は、しっとりとした風情を漂わせる。例年4月中旬から下旬が見ごろだ。

撮影:橋本健次
北区にある世界遺産、上賀茂神社は、正式名称を賀茂別雷(かもわけいかづち)神社と呼ぶ。神代(かみよ)の昔、祭神である賀茂別雷大神(おおかみ)が神山(こうやま)に降臨し、天武天皇の時代に賀茂神宮を造営したのが始まりだ。一の鳥居をくぐり、二の鳥居までの参道脇には、幾本かのシダレザクラが見事な枝を広げる。「斎王桜(さいおうざくら)」の名を持つシダレザクラは薄紅色の花を、その北側にある「御所桜(ごしょざくら)」は、京都御所から孝明天皇が下賜した樹齢150年を超える樹で、白い花が上品な雰囲気を漂わせる。二の鳥居をくぐると最初に姿を見せる細殿(ほそどの)の近くに咲くベニシダレザクラは「みあれ桜」。神の誕生を意味する「御生れ(みあれ)」から、その名は来ているという。例年3月中旬から4月下旬にかけて花見が楽しめる。

撮影:橋本健次
「京の桜の隠れ里」とも呼ばれる北区の原谷苑(はらだにえん)は、木材や苗木を販売する村岩農園が所有する桜苑で、20種400本以上の桜が期間限定で一般公開される。「しだれ桜のジャングル」とも評され、樹齢60年を超えるベニシダレザクラの数は、日本一とも。苑内に足を踏み入れると、ピンク色のシャワーが降り注ぐように咲き乱れ、圧巻だ。例年4月上旬から下旬が見ごろだ。

撮影:橋本健次
古くから桜の名所として知られてきた北区の平野神社は、平安時代に花山天皇が桜を植樹したことに倣(なら)い、皇族や貴族が献花したことに始まる。現在では約60種400本が花を咲かせる。例年3月中旬に、京都でいち早く花をつけるのが平野神社発祥の「魁(さきがけ)」という品種。その後に続き、「寝覚(ねざめ)」「妹背(いもせ)」「手弱女(たおやめ)」「突羽根(つくばね)」など、この神社ならではの品種が次々と美しい姿を見せる。ほとんどの桜は例年4月中旬が見ごろだが、「突羽根」は5月上旬まで花をつける。

撮影:橋本健次
製作著作:KBS京都 / BS11
【放送時間】
京都浪漫 悠久の物語
「写真家と巡る桜の名所~上賀茂神社・鞍馬寺・平野神社・原谷苑~」
2025年4月21日(月) よる8時~8時53分
BS11(イレブン)にて放送