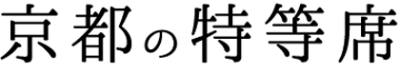宴席から仕出し、おばんざいまで 「ハレ」と「ケ」をめぐる京の食文化<後編>
京都に暮らすうちに、料亭やレストランでいただくごちそうばかりが「ハレ(祝い事や祭り、行事)」の食事ではないと気づきました。それが「仕出し」です。
(BS11『京都画報 初夏・京料理を支える匠の技』より)
(前編から続く)
お食い初めに運動会に、暮らしに溶け込む「仕出し文化」

私の息子のお食い初(ぞ)めの時、京都人の義母が、お赤飯と尾頭付きの鯛(タイ)を仕出屋に頼んでくれました。私が住んでいるところは義父母の地元で、聞けば昔から時々頼む仕出屋だとか。こんなこともありました。京都では、学区の住人の交流を目的とした「区民運動会」が毎年秋に開催されます。町対抗で、老若男女が綱引きやリレーといった競技に一日汗を流す。そこで、昼食に出されたのが仕出屋のお弁当でした。京都の人は誰しも、なじみの仕出屋を一つ二つ持っているものなのかと感心しました。注意して街を見てみると、どの地域にも商店街にも、必ず小さな仕出屋があるのです。

うつわの竹かごを手ずから、「ケ」の場に「ハレ」を届ける
ワインに合う会席料理や和の食材にとらわれない斬新な献立で知られる「木乃婦(きのぶ)」も、元はたった十畳の仕出屋からスタートしたといいます。3代目・高橋拓児さんが「桜を愛(め)でるような」という得意先の注文に際し、うつわとなる竹かごを自ら仕立てる姿には驚きました。

松花堂弁当の中に竹かごをあしらい、筍(タケノコ)の皮を小皿に見立て、桜の花を添える。それだけではありません。竹かごにフタをするようにかぶせた桜の葉を、ひらりとめくって食するというサプライズが仕掛けてあるのです。

料理人が客人のために心を尽くした「ハレ」の料理であることは言うまでもありませんが、食べる人の望む場所へと、それを届けてくれるのが「仕出し」。茶事や法事など改まった席のケースもあるけれど、自宅や職場、地域の集まりといった、注文する人の“ホーム”であることも多いでしょう。日常的な場所だからこそ、「ハレ」の料理が届けば「わあっ」と歓声があがります。

お品書き、色、しつらえ…仕出しとは、工夫して作り出すこと
ケータリングやお弁当、保存食を作る料理人の友人が話していました。「仕出し」には、出前や出張料理という意味のほかに「工夫して作りだす」という意味もあると。コロナ禍でできることが限られているなか、その意味が勇気を与えてくれたと言います。ケータリングという呼び名は現代的ですが、もてなしの心意気は仕出しの時代からきっと変わりません。できたてを食べていただけないからこそ、時間が経ってもおいしい味付けを工夫する。弁当箱を開ける所作や、お品書きの言葉選び、季節を伝える色やしつらえなど、届いてから食べるまでの一つひとつを工夫する。「ケ(日常)」の場に「ハレ」を咲かせるために。

京都の人は、「ハレ」と「ケ」をきりりと区別しています。身内だけのお祝い事や小さな行事でも、家庭料理ではなくプロの味でもてなすことで、喜びの気持ちを伝える。けれど、「ハレ」と「ケ」が光と影のように相反するものだとは、きっと思っていないでしょう。祭りに、行事に、大切な人のもてなしやお祝いに、とびきりの「ハレ」の食卓を整えて願うのはいつも、淡々と続く「ケ」の日々の平穏です。

旅をして出会うのは、京都の「ハレ」の顔かもしれません。けれど、晴れやかな場面に込められた、人の思いと培われた文化に目を凝らせば「ケ」の京都もきっと見えてくる。ここに登場する人々の言葉や仕事、営みが、より深く京都を味わうためのヒントになるのではないでしょうか。

朝日新聞デジタルマガジン&Travel
「京都ゆるり休日さんぽ」に掲載
(掲載日:2021年6月14日)