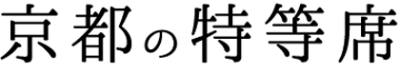食堂のように通いたくなる、京都のビストロ「ブション」のステーキ
「ステックフリット」。塩コショウのみで味付けしたシンプルなステーキにフライドポテトを添えた料理のことを、フランスではこう呼びます。フレンチの肉料理と言うと、美しいソースに彩られたアートのような一皿を想像しがちですが、ステックフリットはフランスの食堂やカフェならばどこにでもある国民的なランチメニューです。旬の味覚やシェフの独創性をふんだんに取り入れた食文化が花開く京都で、変わることなく素朴なフランスの食堂の味を提供し続けているビストロ「ブション」の定番のメニューです。

ミディアムレアに焼かれた牛ハラミの上には、パセリとレモンジュースを合わせたメートルドテルバターがぽってりと。ステーキの余熱でじゅわりととろけ、肉汁とともにお皿にしたたります。お好みで肉にマスタードを付けながら、時に肉汁を吸ったポテトをつまみながら、豪快にほおばるのがステックフリットの流儀。この時ばかりは、カロリーも塩分も気にしてはいけません。プレートに残ったバターと肉汁をバゲットでぬぐって食べ終えたら、メインディッシュはフィニッシュです。

京都市役所の裏手、骨董(こっとう)店や茶舗が並ぶ寺町通からほど近い場所に「ブション」が誕生したのは1999年。当時はまだ少なかった、カジュアルでふだん使いできるフレンチの店としてスタートしました。
ブションとは、リヨンで郷土料理を出す大衆食堂のこと。メニューに並ぶのは、オーナーシェフが得意とするリヨン料理のほか、フランスではなじみ深い定番中の定番ばかり。日本人の好みに寄せて、多品目の食材をバランスよく使ったり、季節に合わせた料理を提供したりすることはほぼなく、オールドスタイルなフランスの食堂を貫いてきました。

赤いギンガムチェックのテーブルクロスも、隣のテーブルとグッと距離が近い客席の配置も、どこかフランスのビストロの風景を思わせます。京都の街なかにありながら、一歩店に足を踏み入れるとそこには本場の空気が流れ、国際色豊かな客層が自由に食事を楽しんでいるーー。多彩なビストロが街にあふれる昨今でも、ブションが愛され続けているのはそんなスタイルゆえ。淡々と、昔ながらの味を気取りなく供する姿勢は、京都の老舗にも通じるものがあります。

「特別な日にいただくフレンチのディナーがある一方で、うちで出しているのは日常的な料理。肩ひじ張らずに食べられるから、“初めてのフランス料理”に選んでいただくこともあります」。そう話すのは、ブションで約20年スタッフを務める玉田裕一さん。「ステックフリットも、当初はもっと肉が硬かったですよ。日本人は柔らかくてとろけるような肉が好きだけど、赤身肉を好むフランス人にとっては“肉はかみしめてよく味わうもの”で。この店を続けてきたことでお客さんもこうした食文化になじみ、楽しむようになったんだと思います。昔に比べると肉質が良くなり、ずいぶん柔らかくなりましたし」と笑います。

確かに、ブションのステーキはしっかりと弾力のありそうな見た目に反して柔らかく、心地よい歯ごたえを感じながらフォークを進めることができます。かむほどにあふれ出る肉汁に、自然と胃袋がパンとワインを求めます。その味と食感は鮮やかに記憶に残り、「今日はお肉の気分だな」という日に、真っ先に頭に浮かぶ不思議な力があるのです。まるで、通い慣れた地元の食堂の味を思い出すかのように。

日々、ブションのホールでお客様を迎える玉田さんは言います。「同じことをしているようで、毎日は少しずつ違います。観光客の方が来てくださったり、京都に住む方がいらしたり、久しぶりにお会いするお客さんだったり。でも、続けているからこそ、また会える人がたくさんいます」。世界中から人々が訪れ、さまざまな食文化が交差する京都だからこそ、「いつもの味」がそこにあるという喜びがある。食べた人を虜(とりこ)にするステックフリットは、何度でも“食堂”の扉をたたきたくなる魔法のひと皿です。(撮影:津久井珠美)

ブション
http://www.bellecour.co.jp/bouchon%20file/bouchon.htm

朝日新聞デジタルマガジン&Travel
「京都ゆるり休日さんぽ」より転載
(掲載日:2019年3月22日)