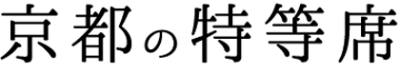笑顔を見に帰りたくなる、実家のようにあたたかな「喫茶チロル」
三角屋根の壁に掲げられた「COFFEE」の文字。赤と黒のストライプのひさし。洋館風のレトロな鉄格子。それらが目に入るとなぜかほっとして、つい扉を開けたくなる喫茶店が「喫茶チロル」です。二条城のおひざ元で創業し、50余年。ドアの向こうには、常連客から「お母さん」と慕われる女性とその家族の、穏やかな笑顔がありました。
■暮らすように、小さな旅にでかけるように、自然体の京都を楽しむ。朝日新聞デジタルマガジン&Travelの連載「京都ゆるり休日さんぽ」はそんな気持ちで、毎週金曜日に京都の素敵なスポットをご案内しています。 (文:大橋知沙/写真:津久井珠美)
心落ち着く空間で、働く人の止まり木になれたら

「朝8時や言うてるのに、7時に来はる人がいるんですよ。開けなしゃあない。お客さんあってのチロルやから。京都駅からタクシーでここまで来はる人もいるし、30年毎日通ってくれてる人もいます。『ここへ来んと1日が終わらへん』って」

朗らかにそう話すのは、先代の妻で、84歳の今も現役で店に立つ秋岡登茂さん。創業から50年以上朝の6時半に開店していましたが、登茂さんのケガやコロナ禍の営業自粛を経て、現在は午前8時にオープン。けれど、以前からの名残でいまだに朝早く訪ねてくる常連さんがいると笑います。

「クラシックや本が好きで、元山岳部の夫が、当時勤めていた会社が倒産して始めたお店です。せやから、私らコーヒーも料理も素人! それでも、夫が言うてた『働き蜂の止まり木』になれたらと思ってね。自己流で、みんなでなんとかやってきたんですよ」

山小屋をイメージしたという店内は、大工だった登茂さんの父や親戚と協力して作り上げたもの。珍しい木製のシャンデリアも、壁に飾られた古き良き京都の街の写真も、セピア色に色あせたテーブルも、先代が選び、家族で守ってきたチロルの財産です。

厨房(ちゅうぼう)を担当する2代目の誠さんが仕込むカレーが、チロルの名物。店を継いでからは誠さん独自に改良を重ね、数十種類もの材料を煮込んだ特製ルーに仕上がりました。「どんどん増えていって、もうどれをなくしてもいいかわからんようになってしもたんです」と誠さんは笑います。懐かしくて素朴ながら、いつまでも余韻が残る複雑な風味はクセになる味。ふいに「チロルのカレーが食べたい」と記憶がよみがえってくるような、不思議な引力があります。
みんなが安心する、実家のようなあたたかい「居場所」

「元離宮二条城」が世界遺産に登録され、周辺にさまざまな店が立ち並ぶようになると、地元客だけでなく観光客や修学旅行生も多く訪れるようになりました。リーズナブルでおなかいっぱいになれるカレーは、地元の高校生や一人暮らしの大学生にも大人気。学生たちが、チロルのテーブルで勉強やデートをしている光景も珍しくありません。
「京都に下宿で大学に通ってはる学生さんらの『にわか母さん』になれたらと思ってるんです。知らない街で話し相手がおらんとさびしいやろう? 人間はやっぱり話さなあかん。類は友を呼んでね、ここに来る人はみんなおしゃべり」

チロルを訪ねて来る人は、そう言って笑う登茂さんの顔が見たくて扉を開けるに違いありません。店には、京都を拠点に活動する劇団「ヨーロッパ企画」やイラストレーターのナカムラユキさんなど、チロルを愛してやまないクリエーターが寄せた作品やノートが残ります。何年も前にアルバイトしていた学生から、今でも手紙が届くといいます。毎日同じ席でコーヒーを飲む人も、ここでデートして結婚して子どもを連れてくる家族も、数年ぶりに京都を訪れて「まだつぶれてなかったんか!」と笑って冷やかす人も……。チロルを訪ねてくる人々の物語は毎日更新され、秋岡さん家族は飽きることがありません。

「人生は不思議なもの。まさか喫茶店をやるとは思わなかったですよ。ホットケーキもアイスクリームも目新しいもんは何にもない店ですけど、みんなで労わりあって、心豊かに働けたらね」
登茂さんの言う「みんな」は、一緒に働く家族はもちろん、チロルを愛してくれる人々全てを意味しているのでしょう。家と職場や学校の間に、旅や引っ越しで訪れた土地勘のない街の中に、理由などなくてもおしゃべりできる居場所がある。その心強さとほっとする気持ちは、一度チロルを訪ねたらきっとわかるはずです。


朝日新聞デジタルマガジン&Travelより転載
(掲載日:2020年10月23日)