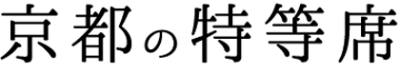第33回「京のえべっさんの福笹 / 京都ゑびす神社」
新年が明けまして1月10日前後のお祭り。「えべっさん」の名で親しまれる京都ゑびす神社の『十日ゑびす大祭(十日ゑびす)』をご存じでしょうか。この時期、京都ゑびす神社の周辺を歩くと、京都ゑびす神社で授与される色とりどりの縁起物をつけた「福笹(吉兆笹)」を持つ人に多く出会います。

そして、あちらこちらから、“商売繁盛で笹もってこい”という威勢の良い掛け声を聞くはずです。この言葉には、「ゑびす神社に笹を持ってきたら、その笹は福笹となって、あなたのお商売が繁盛するよ」という意味が込められています。

福笹とは、えびす様のお札や、鯛や小判を模した飾りを笹の枝に付けた縁起物で、この時期だけ受け取ることができる特別なものです。
また、笹は生命力に溢れ、京都ゑびす神社では家運隆昌、商売繁盛の象徴とされています。私も大好きな植物です。
福笹を授与される神社といえば、兵庫の西宮神社や大阪の今宮戎神社も有名ですが、福笹に関しては、実は、この京都ゑびす神社が発祥なのだそうです。
福笹を求めるお詣りの人たちはもちろん、神社の周辺には、りんご飴やベビーカステラなどの露店が並ぶなど、独特の活気に溢れ、“十日ゑびす”の賑わいは、新春の京都の風物詩のひとつとなっています。

京都ゑびす神社の歴史は古く、約800年前の西暦1202年に岡山市より遷座されました。本殿は新しい建物に見えますが、昔からの建物を守るために囲むように建てられているそうで、内側には300年前の本殿も残されているそうです。
ところで、私は、以前よりこの福笹がとても好きで、京都のさまざまなお店の店内や、職人さんの工房の高いところに飾られるのを見つけるたびに、その福福しく愛嬌のある縁起物にとても魅力を感じて、一度、絵にも描いてみたいと思っていました。
そうして、4年ほど前に神社でいただいた福笹を作品に描いて、そのまま画室に飾ったことがきっかけで、“十日ゑびす”には毎年欠かさずに京都ゑびす神社にお詣りをして、新しい福笹をいただくようになりました。

私は自然の中にある花をしっかりと写生したうえで比較的繊細に丁寧に描く作家ですから、その福笹の絵は、当初はほんの遊び心とおまけの作品のつもりでした。しかし、個展に出したところ好評で、さらに、あの「えべっさん」を自分にも描いてほしいとのご依頼が関西のお客様を中心に今も続いていて、えびす様と福笹がいかにこの地の人々に愛されているかを感じています。

今年も、福笹を受け取り、神楽鈴や宝船などの飾りをつけてもらい、本殿でえびす様に新年を豊かに健康に迎えられた感謝を伝え、自分と大切な周囲の人たちのますますの福徳をお祈りしました。
みなさまにも、このお便りから京都の新年と“十日ゑびす”の活気が少しでも伝わって、今年1年の商売繁盛、家内安全、開運招福…たくさんの良きことが届きましたら嬉しいです。素晴らしい年となりますように!