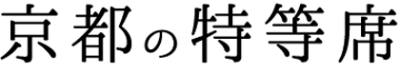20190816OPHO0128AGOC.jpg)
先祖の霊「オショライさん」を見送る灯 五山送り火が伝えるもの
京都では、先祖の霊のことを「オショライさん」と呼びます。なんだか親しみのわくこの呼び名、京都に移り住んでから、お盆の時期になるとたびたび耳にするようになりました。心から慕っていた親戚や隣人のように、亡き人の魂を「今そこにいるかのように」そう呼ぶのです。
20200816OPHO0100AGOC.jpg)
あの世とこの世を、オショライさんは「火」を道しるべに行き来します。毎年8月7日から10日、六道珍皇寺(ろくどうちんのうじ)で行われる「六道まいり」は、お盆に私たちの元へと帰ってくるオショライさんを迎える行事。ちょうちんに明かりがともり、「迎え鐘」が響きます。六波羅蜜寺で8日から行われる「萬燈会(まんどうえ)」をはじめ、京都のあちこちで明かりを使った盆行事が。盆の入りの13日、苧殻(おがら)に火をつけ「迎え火」とする風習を、今でも行う家もあります。ご先祖さまの霊が迷わないように、明かりや火をともしてお迎えするというわけです。
鳥居形20190806/GettyImages-1171621003.jpg)
あの世へ帰るオショライさん、送り火に手合わせる人々
「五山送り火」は、現世に帰ってきたオショライさんを、再び冥土へと送り出す行事です。そのスケールの大きさから、すっかり京の夏の風物詩として観光名物になりましたが、本来の意味は亡くなった人や先祖の霊を供養し、お見送りすること。8月16日の夜、橋の上や交差点で送り火を眺める人々を見渡すと、静かに手を合わせる人の姿がそこかしこにあります。
20190816OPHO0128AGOC.jpg)
五山の中で最初に点火される、東山如意ヶ嶽(にょいがたけ)の大文字。点火時刻の午後8時前になると、鴨川の土手に、高台に、見晴らしの良い交差点に、次々と人が集まります。ほんのり昼間の暑さを残した夜の住宅街から、わらわらと人が出てくる様子はなんだか不思議。ある人は夕食の片付けの手を止めて、ある人はうちわを片手にステテコ姿で、ある人は子どもたちの手を引いて。老若男女さまざまな人が、まるで遠くから誰かに呼ばれたかのように、出てくるのです。
「ついた?」「ついたついた」「全部ついたわ。次はどっちや」
妙法(撮影年月日不明)/GettyImages-1023233266.jpg)
東から反時計回り、5分おきに点火予定
東から北を回り西へと、五つの送り火は約5分おきに順に点火され、やがて、五山すべてに炎の文字が浮かび上がります。大文字、妙・法、船形、左大文字、鳥居形。すべての送り火が一望できる場所は、市内に数えるほどしかありません。多くの人は、自分の住む地域から見える範囲の送り火を追いかけるようにぞろぞろと移動し、無事ご先祖さまを送る火がともったことを見届けて帰路につきます。
180817-0130.jpg)
いつ、誰が、何のために送り火を始めたのか。実は、俗説はあるものの確かなことはわかっていません。最初の送り火である如意ヶ嶽の大文字は、弘法大師が山に「大」の字を書いたという伝説から、足利義政が若くして他界した息子・義尚(よしひさ)の菩提(ぼだい)を弔うためという有力説まで、さまざまな説があります。
送り火の記録が初めて文献に登場するのは、1603(慶長8)年。公家・舟橋秀賢(ふなはし・ひでかた)の日記『慶長日件録』の7月16日の条に「晩に及び冷泉亭に行く、山々灯を焼く、見物に東河原に出でおわんぬ」と記されていることです。その後、年を追うごとに他の送り火について記述された文献が発見されており、江戸時代初期には年中行事として定着していったことがうかがえます。以降、現代にいたるまで400年以上もの間、送り火は京の人々の手によって守られてきたのです。
180817-0046.jpg)
翌日登山、送り火の「消し炭」拾い
送り火の翌日、火床に残る炭を求めて、早朝から如意ヶ嶽に登る人がいます。この炭は「消し炭」と呼ばれ、半紙にくるんで水引をかけ、玄関につるしておくと厄よけになると伝えられています。オショライさんを送った火には、先祖の守護が宿ると考えられていたのでしょう。送り火を見届ける京都の人々のまなざしとこうした風習を思うと、目には見えなくとも確かに、オショライさんがここにいたのだと実感するのです。
船形・左大文字(撮影年月日不明)/GettyImages-1023226944.jpg)
迎え火で先祖の霊を迎え、それぞれの家でもてなして、送り火であの世へとお見送りする。オショライさんは、温かく、優しく、ちゃめっ気があったり豪快だったりしたあの人やあの人の姿です。
送り火の夜、皆誰かに呼ばれたかのように定刻になると外に出るのは、こういう声が聞こえているのかもしれません。
「そろそろオショライさんが帰らはるで」
「ほな、そろそろ帰りますわ」
【放送情報】
生中継!京都五山送り火2021
2021年8月16日(月)よる7時00分~8時53分
BS11(イレブン)にて放送

朝日新聞デジタルマガジン&Travelより転載
(掲載日:2021年8月10日)