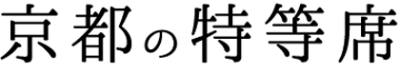可憐な花咲く社寺で、ゆかりの物語を知る
春の神社仏閣巡りでは、このシーズンならではの美しく咲き誇る花を愛でてみたい。
平安時代初期、弘法大師空海によって創建された右京区の平岡八幡宮は、椿の名所として知られる。2025年は3月14日から4月6日まで「椿を愛でる会」(無料)を実施し、境内いっぱいに咲き誇る約200種300本の椿が観賞できる。樹齢500年超えのヤブ椿や、葉が金魚の形に見える金魚葉椿のほか、「願掛けをしたところ、一夜で咲き、願いが成就した」という伝説が残る白玉椿など、さまざまな椿が訪れる人を迎えてくれる。椿だけでなく、通常非公開の本殿内陣の天井のマス目に、椿やボタン、ショウブなど44枚の植物が描かれた「花の天井」も見ものだ。こちらは3月14日から5月6日の「春の特別拝観」(拝観料800円)で特別公開される。

山科区の隨心院(ずいしんいん)は、平安の歌人で“絶世の美女”と謳われた小野小町(おののこまち)が余生を送った場所といわれる。境内にある「小野梅園」には、遅咲きと知られる摩耶紅梅(まやこうばい)や白梅、薄紅梅など、およそ200本もの梅が咲き誇る。摩耶紅梅の色は古来「はねず色」と呼ばれ、別名「はねずの梅」とも呼ばれる。毎年3月の最終日曜に行われる「はねず踊り」は、はねずの梅が咲くころに、子供たちが小野小町の逸話を題材にした踊りを踊っていたことに由来する。大正時代に途絶えたが、1973年に寺と地域住民によって復活し、現在では伝統行事として受け継がれている。

中京区の繁華街、新京極商店街の一角にある誠心院は、平安の歌人・和泉式部(いずみしきぶ)が初代住職を務めたと伝わる。平安時代中期、和泉式部が仕えていた藤原彰子(ふじわらのしょうし)のすすめで、父・道長が建立。境内には式部の宝篋印塔(ほうきょういんとう)があり、毎年、命日にあたる3月21日には、本堂でゆかりの謡曲(ようきょく)が奉納され、午後には「開山和泉式部忌」と「春のお彼岸法要」が行われる。またこの頃になると、式部が生前愛した「軒端(のきば)の梅」にちなんで植えられた梅の木が可憐な花を咲かせ、参拝客の目を楽しませてくれる。

北区鷹峯(たかがみね)の常照寺は桜の名所として知られ、例年3月下旬から咲き始め、4月中旬にかけて見頃を迎える。参道ではソメイヨシノが出迎え、境内はヤマザクラやシダレザクラなど約100本の桜に染められる。江戸時代に「天下の名妓(めいぎ)」と称された2代目・𠮷野太夫は、開山(かいさん)の日乾(にちけん)上人に深く帰依(きえ)し、山門を寄進。そんなゆかりから、毎年4月の第2日曜には「𠮷野太夫花供養」が行われ、「内八文字(うちはちもんじ)」を踏みながらゆっくりと進む、優雅な「太夫道中」の姿を見ることができる。

製作著作:KBS京都 / BS11
【放送時間】
京都浪漫 悠久の物語
「春の京都 とっておき花物語」
2025年3月17日(月) よる8時~8時53分
BS11(イレブン)にて放送