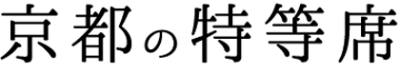BS11_12jigo1_top.jpg)
和菓子と洋菓子の間に流れる物語 日本唯一の金平糖専門店「緑寿庵清水」
できあがるまで2週間 昔ながらの製法で
「金平糖というと、和菓子になるんですか? 洋菓子になるんですか?」
と素朴な疑問を口にする、俳優の常盤貴子さん。江戸時代後期の1847(弘化4)年、左京区の百万遍(ひゃくまんべん)に創業した日本で唯一の金平糖専門店「緑寿庵清水(りょくじゅあんしみず)」を訪ねての一言です。
BS11_12jigo1_1.jpg)
「元々は千利休さんがお茶事用としてお使いになられたんですけれども……」
そう答えるのは、「緑寿庵清水」5代目女将(おかみ)・清水珠代さん。ポルトガルから伝わった南蛮菓子「コンフェイト」が金平糖のルーツで、織田信長はその形と味にたいそう驚いたとか。当初は身分の高い人しか口にすることのできない、貴重なお菓子だったそうです。
BS11_12jigo1_2.jpg)
それもそのはず。現在でも製造には約2週間を要しますが、「緑寿庵清水」の初代のころはできあがるまで3カ月もかかったのだそう。大きな釜で絶えずかき混ぜながら蜜をかけ、金平糖が星形に結晶化していくまで釜を回し続けます。
「鍾乳洞が何百年、何千年とかけて伸びていく原理と全く一緒で。蜜をかけると釜にふれるところとふれないところが出てくる。ふれたところだけが熱いので、水分が蒸発して砂糖の結晶として残っていくというわけです」と、5代目・清水泰博さんは語ります。
BS11_12jigo1_3.jpg)
これほどの手間と時間のかかるお菓子が、千利休の時代どれほど貴重で、珍しいものだったか。想像するに難くありません。宝石のようにきらめく見た目も、茶事の客をさぞ喜ばせたことでしょう。お菓子はいつの時代も、ふるまう相手を驚かせ、感動させたいというもてなしの心が育んできたのです。
ワイン味の「究極の金平糖」 日本で独自にアップデート
そういえば、常盤さんが京屋敷の文化サロン「有斐斎弘道館(ゆうひさいこうどうかん)」を訪れた際、出迎えた同所理事で老舗和菓子店「老松」4代目当主・太田達(とおる)さんは、こんなサプライズでもてなしていました。表千家の初釜で決まって登場するお菓子「常盤饅頭(まんじゅう)」に、常盤さんの思い出の愛車を描いたのです。感激に目を潤ませる常盤さんを前に、太田さんも喜びの表情を浮かべていました。
BS11_12jigo1_4.jpg)
形やルールを重んじる印象が強い和菓子の世界ですが、その歴史は常に新しいものを求め、成熟してきました。核にあるのはいつも、相手を喜ばせたいという気持ち。すでに定型化し、完成したようにみえる金平糖も、その例外ではなかったようです。
「ずっとお砂糖の味の金平糖しかなかったんですね。それを4代目が、お客様に喜んでいただける金平糖を作りたいゆうことで、現在のようなお味のついた金平糖を開発しました。3代目は『味のついたもんなんか邪道や』と言って大反対してたんですが、できあがったもんを食べてみて『やっぱりおいしいもん作らなあかんな』と賛成してくれはって」(清水珠代さん)
BS11_12jigo1_5.jpg)
今、「緑寿庵清水」では4代目の考案した多彩な味に加え、チョコレートやワイン、ブランデーといった、製法上金平糖にすることが難しかったフレーバーに次々と挑戦し「究極の金平糖」として人気を博しています。加熱で風味が飛ばないよう独自の製法を研究し、金平糖としての歯ざわりを生かしつつも、まるでワインやブランデーをいただいているような芳醇(ほうじゅん)な風味に。作る数が限られているため完全予約制で、毎年完売後もキャンセル待ちの申し込みが後をたちません。
BS11_12jigo1_6.jpg)
「(以前)4代目が、金平糖のルーツを探りにポルトガルまで渡ったのですが、今はポルトガルでは全く作っておられなくて。最後の一軒のところで、『これが最後の金平糖だから、あなたが日本に持ち帰って、日本の伝統文化として発展させてください』と使命をいただいたんです」(清水珠代さん)
BS11_12jigo1_7.jpg)
金平糖は和菓子か洋菓子か? この問いに簡単に答えられない理由が、珠代さんの言葉で伝わったのではないでしょうか。金平糖には、国を超え、時を経て、伝統を更新しながら紡がれてきた物語があります。信長が驚き、利休がもてなした星くずのような甘い粒は、今も私たちにささやかなサプライズを届けてくれているのでしょう。
■ 京都画報 第3回「京の和菓子」
BS11オンデマンドで12月26日正午まで無料で視聴可能。
番組公式ホームページはこちら。
【次回放送情報】
■京都画報 第4回「うつわの彩り」
2022年1月12日(水)夜8時~
京都は清水焼に代表される焼き物“京焼”が発展した土地。茶の湯や懐石料理など、うつわと親しむ文化が育った土地柄、京都人は目利きぞろい。普段使いできる新作から、目がくらむようなアンティークの逸品まで様々な楽しみ方ができる うつわ。京都で花開いた豊かなうつわ文化の世界へご案内します。

朝日新聞デジタルマガジン&Travelに掲載
(掲載日:2021年12月15日)