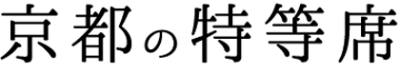未来のアンティークになり得る、現代の作家のうつわに出会う旅
鑑賞やコレクションではなく、暮らしに寄り添ううつわ
京都のうつわを育ててきたのは、茶の湯と食文化。茶人や料理人、そして目も舌も肥えた客人たちが、どんなうつわでもてなし、もてなされるのか。競い、高め合ってきました。その切磋琢磨(せっさたくま)は、うつわを提案する店も同じこと。常盤貴子さんが訪ねた「うつわや あ花音(かね)」もその一つです。

京都ゆかりの作家を中心に、およそ40人の陶芸家の作品を扱う「あ花音」は、南禅寺門前に店を構え創業32年を迎えるうつわ店。骨董(こっとう)や京焼・清水焼といった京都のうつわ選びの選択肢に、「同時代の作り手のうつわ」をいち早く提案してきました。

2カ月に一度のペースで開く企画展では、食材や季節に合わせたテーマに沿って、それぞれの作り手が個性豊かなうつわを披露します。中でも「よろしゅうおあがり」と名付けられた企画展では、料理人とタッグを組み、展示に寄せられた作家のうつわで料理をいただく会を開催。うつわと料理の美しい化学反応を、目でも舌でも楽しむことができるのです。

「うつわは料理を盛って初めて完成するので」と語るのは、オーナーの梶裕子さん。その言葉からは、飾り、コレクションするためのうつわではなく、使う人とともに暮らしを歩むうつわであることを大切に、作品を提案してきたことがうかがえます。今回は「よろしゅうおあがり」で料理を担当してくれているイタリアンレストラン「オルテンシア」で、常盤さんが選んだうつわを使って料理をふるまってくれることになりました。さて、常盤さんが選んだうつわは……?
うつわ×料理 十人十色のうつわの魅力を未来へ

まず常盤さんが手に取ったのは、多角形のフォルムと銀彩がシックな山本哲也・作「sabi-刷毛目銀彩入隅長皿」。シンプルながらも釉(ゆう)薬の流れに表情がある、伊賀上空見子・作「平皿 茶」と、梶さんのアドバイスで選んだ藤田佳三・作「紅安南 菓子鉢」の3点です。

うつわを選び、料理で応える。その往復書簡のようなやりとりに返信するのは、「オルテンシア」のシェフ・那須嵩之さん。イタリアでの修業を経てオープンし、ミシュラン・ビブグルマンを2年連続で獲得する人気店です。

「実は、こちら(四角い皿)が一番、僕の中では難しい。ふだん丸のお皿がほとんどなので」と笑いつつも、那須さんの手にかかればクールな表情のうつわもぐっと柔らかく。スライスレモンの色が橋渡しとなり、うつわと食材の色をつなぎます。

「モッリーカ(味付けパン粉)のオレンジの色とカラスミの色が、(お皿の茶色に)合うんじゃないかと思って」と那須さんが供したのは、オレンジ色の粉が一面に降り積もったパスタ。カラフルな紅安南手の鉢には、那須さんのイタリア修業の集大成だというシチリアの郷土料理「マタロッタ」が盛り付けられました。現代の和食器がイタリア料理と出会い、空っぽのうつわからは想像もできなかった新たな景色を描きます。

「(シチリア料理は)同じ料理でも十人十色。盛り付け方も変われば、使われる食材も変わってきます。そういうところがすごく魅力的に感じましたね」と那須さんは語ります。

うつわもきっと同じです。何を選び、何を盛り、どう使うか。さまざまな茶人や料理人がそうしてきたように、私たちもまた、十人十色にうつわを選び、使う生活者です。選ぶことは、自分の好みと向き合うこと。そして暮らしを見つめること。だからうつわは楽しく、尽きない魅力があるのでしょう。

「あ花音」の梶さんはこう語ります。
「私の名刺の後ろには“antique for the future”って書いてあるんです。お客様の元で作品が大切にされて、次につながっていくような、そういうものになったらいいなと思っていて。いつか愛されて未来の骨董になったらいいなと思っています」
北大路魯山人の五客の皿に、魯山人の哲学を見るように。今この時代のうつわを後世の人が見たら、何を思うのでしょう。どんな人が作り、どんな料理を受け止め、どんな人に使われていたのか。そんなふうに想像される未来を思うと、私たちも一人の、文化の担い手であると気づくのです。
■京都画報 第4回「うつわの彩り」
BS11オンデマンドにて、1月26日(水)よる9時まで見逃し配信中。
番組公式ホームページはこちら。
【次回放送情報】
■京都画報 第5回「至高の京宿 気品と美の系譜」
2022年2月9日(水)よる8時~
幕末の志士をはじめ、皇族や小説家、世界的映画俳優のチャップリンなど数多くの著名人が宿泊されてきた「柊家」。昭和天皇の義理の弟君、東伏見宮家の別邸として建てられ、これまで数々の皇族が滞在してきた「吉田山荘」。老舗旅館の中でも最高峰の京宿の品格は、どのように守られ受け継がれてきたのでしょうか。京都の文化と共に時を重ねて佇む宿の歴史と人々を惹きつけてきた魅力に迫ります。

朝日新聞デジタルマガジン&Travelに掲載
(掲載日:2022年1月19日)